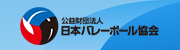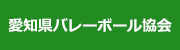小学生で見た春高「成徳に行きたい!」
バレーボールとの出会いは、小学1年生の時。「ピアノの先生になりたい」と思っていた少女の心を動かしたのは、友人の熱心な誘いだった。
「『一緒に全国に行こうよ!』って。周りより少し背は高くて運動もできたけど、特別だったわけじゃない。最初は断り続けていたんですけど、春高や日本代表の試合をテレビで見るようになって、面白そうだな、と思うようになった。いろいろ迷って、3年生からバレーボールを始めました」
入る前は週4日と聞いていた練習も、入部すると週5日に変わり、空いた日はピアノのレッスン。小学生のうちはどちらも両立してきたが、さすがに時間がない。ピアノも続けたい思いはあったが、バレーボールで仲間と一緒に同じ目標を持って戦う楽しさに触れ、気づけば夢中になっていた。
4年生からはセッターも経験し、5年生になって試合出場の機会が増えれば、その結果によって叱責されることも増える。ただ純粋に「楽しい」だけではない厳しさも経験し、それまではあっという間だった練習をひたすら長く感じ、練習へ向かう足が重くなることもあったが、それでも「やるならやり抜け」と後押しする存在がいた。元高校球児で社会人野球選手としても活躍した経験を持つ父だ。野球とバレーボール、競技は異なるが、本気で日本一を目指し、プロの世界も夢見て野球に取り組んできた父はスポーツに本気で取り組む厳しさを教えてくれる存在でもあった。
そしてもう1つ、今へとつながる大きな転機も訪れた。セッターからスパイカーへ転向した小学6年生の時に何げなく見た、春高バレーの準決勝だった。
決勝進出をかけて戦うのは、三連覇がかかる大分代表の東九州龍谷と、東京代表の下北沢成徳。東九州龍谷の鍋谷友理枝と下北沢成徳の大竹里歩、両チームのエースによる壮絶な打ち合いを東九州龍谷がフルセットで制したのだが、高いトスを高い打点から打ち切る成徳バレーがまだ幼い吉永の心をつかんだ。
「この高校に行きたい、ここでこのバレーがしたい、と強烈に思ったんです。いつかこのチームから誘ってもらえる選手になるために頑張る。夢ができた瞬間でした」

最高のライバルと戦った忘れられない関東大会
瑞穂野中に入学と同時にピアノを辞め、それまで以上にバレーボールに明け暮れた。全国大会出場、さらに全国で勝つチームになるためには、栃木県内だけでなく関東各地の強豪校との練習試合も組まれる。特にゴールデンウィークや夏休みなど、長期休暇になれば必ず決まって互いの学校を行き来しながら合宿を組んできたのが、東京の共栄学園だ。全国優勝を争うという面で見ればライバルではあるが、共に切磋琢磨しながら強くなる。チームは違っても同じ目標に進む仲間で「一緒に全国へ行こうね」と口にしてきた。
それなのに。時に運命は残酷だ。
中学3年時、全国大会出場をかけた関東大会の組み合わせを見て、吉永は愕然とした。吉永だけでなく、瑞穂野中の選手も共栄学園中の選手もきっと全員が同じ。関東で8チームしか出場できない全国大会へ向けた関東大会の2回戦で、両校が対戦することになったからだ。
「全国大会が富山で開催されるので、いつも合宿のたびに『ラスト、富山で一緒にやるしかないよね』って話していたんです。それなのに2回戦で当たってしまったら、どっちかしか行けない。何でよりによってここで共栄なの?って思いました」
何度も何度も戦ってきた相手だけに、手の内はわかっている。全国大会という舞台を目指し、互いが本気でぶつかり合った試合は25点では決着がつかず、30点を超えた。そしてそんな“激闘”を制し、全国大会出場を果たしたのは吉永のいる瑞穂野中だった。
長い長い戦いを称える拍手が会場から送られる中、この試合で全国が絶たれた共栄学園の選手たちが泣き崩れているのが見えた。
「勝てたことは嬉しかったけど、共栄の選手たちの顔は見られなかった。でも、会場の拍手や、涙を見て、絶対に、もっともっと頑張らなきゃいけないと思ったことは今でもすごくよく覚えています」

まさかの「リベロ」で見つけた自分のプレースタイル
憧れの下北沢成徳高に初めて足を踏み入れたのも、中学3年の時。練習を見に来ないか、と誘いを受け、夢の場所へ。胸躍らせる気持ちが、目の前で行われる練習を見て吹っ飛んだ。
「ちょうど春高前だったので、ピリピリした空気、ムードが漂っていて、私なんかがここにいちゃ行いけないだろう、と怖くなったし、『私本当にここでやっていけるの?』って強烈に思ったんです。これから自分がとんでもないところに足を踏み入れようとしているんだ、と改めて実感しました」
全国の強豪校に留まらず、常に目標は日本一。多くの日本代表選手も輩出する名門校に集まる選手のレベルも想像以上で、入学して間もなく、吉永の心も折れかけた。当時の身長は168センチ。中学ではエースとして活躍したが、ネットの高さも変わり、試合へ出るためには自チームのポジション争いにも勝たなければならない。1学年上には石川真佑がいて、2学年上には岩澤実育。後に日本代表でも中心となる選手たちが顔を揃える中、チームを率いた小川良樹監督から吉永に、ポジションの変更が告げられた。
「『1回リベロをやりなさい』と言われて、『私にはチャンスがなくなった』と思いました。真佑さんだけじゃなくアタッカーも揃っていて、リベロには実育さんがいる。その中でリベロと言われても試合に出られるはずがないし…。スパイカーとしても勝負できないのか、と思ったらものすごくショックでした」
諦めもあり、練習にも身が入らない。当然、そんな姿勢を小川監督が見過ごすわけがなかった。
「リベロをすることをマイナスに考えているかもしれないけど、君の身長では、上に行くためにはレシーブができないと難しいんだよ」
その言葉で、一気に意識が変わった。
「中学までは小さくてもチームの中では攻撃の中心。他に守備がうまい子もいたので、レシーブでカバーしてくれていたんですけど、これからは私がその役割を担わないといけないんだ、と気づかされました。それからはとにかくレシーブ力を上達させるために、毎日必死で練習した。今のプレースタイルができたのは、あの時、成徳でリベロを経験しなさい、と言われたおかげです」

夢破れた春高、人生初の主将。すべての経験がつながる時
レシーブ力を高め、ディフェンス力も備えたアウトサイドヒッターとして3年時にはインターハイで3位に入り、国体は優勝。最後の春高で日本一を目指したが、夢は、東京予選で潰えた。
13年連続出場が途絶えてしまったことも重なり、当時を思い返すと「自分たちのやってきたことは間違っていない、と正当化するのが精いっぱいだったけれど、次の日に学校へ行くこともつらかった」と言うように、今でも胸が痛む。
「あの頃の試合や映像を見なきゃいけない、とわかっていても見られない。悔しいというよりも、やってしまった、という思いは消せないです」
だが、中学時代にライバルとの忘れられない試合を制した経験や、リベロという考えもしなかった経験がその先へとつながっていったように、高校最後の大会で味わった消えることのない後悔も、今へとつながる糧になる。下北沢成徳高を卒業し、東京女子体育大へ進学し、「人生初」のキャプテンという立場に就き、周りを動かす立場になった時、さまざまな経験が力になって活かされていることを実感した。
「成徳も自主性を重んじるチームでしたが、大学はそれ以上。練習メニューも自分たちで考えて、いかにチームを同じ方向へ向かせるか。うまくいくことばかりじゃなく、失敗して、ガタ落ちすることもあるんですけど、でもじゃあそこからどうするか、また考えて成長できる。大学4年間で人として本当に成長することができたと思うし、その時間が、まさに今、ここでつながっていると思うんです」

副将として目指すは「邪魔くさいと思わせる選手」
2024年、東京女子体育大を卒業した吉永は、クインシーズ刈谷に入団した。
ルーキーイヤーから出場機会をつかみ、好守で抜群の安定感を発揮。2年目の今シーズンは副キャプテンに就任した。当初は「何で自分が?」と驚いたことを明かすが、重ねた経験の中に理由を見つけることができた。
「高卒の選手も多いチームで、(在籍)7年目の(キャプテン鴫原)ひなたさんを支える立場だけじゃなく、下の子ものびのびできる環境をつくる。私の今までの経験がまさに活かせる、活かすべきじゃないか、って。身長が大きいわけじゃないし、華があるわけでもない。でも、チームが困っている時はどんな形でもいいから率先して助けたいし、相手からすれば『あの選手がいると嫌だよね』とか『ねちっこくて邪魔くさいなぁ』と思わせる存在になれたら最高ですよね。自分だけじゃなく、周りを活かせる、そういう選手になりたいです」
2年目のSVリーグ。新体制で迎えるシーズンは、新たなメンバーも加わり、日々の練習でチームの形が固まりつつある実感もある。
「目指すのは優勝。みんなが口に出して、優勝という同じ目標を見据えて進んでいるので、大事な試合、大事な場面で積み重ねてきたことを自信にして戦えるように。それがいい結果、成績につながればベストな形になれると信じているので、1つ1つ、大事に積み上げていきたいです」
クインシーズの要、欠かせぬ存在として、いかなる時もチームのために戦い続ける。
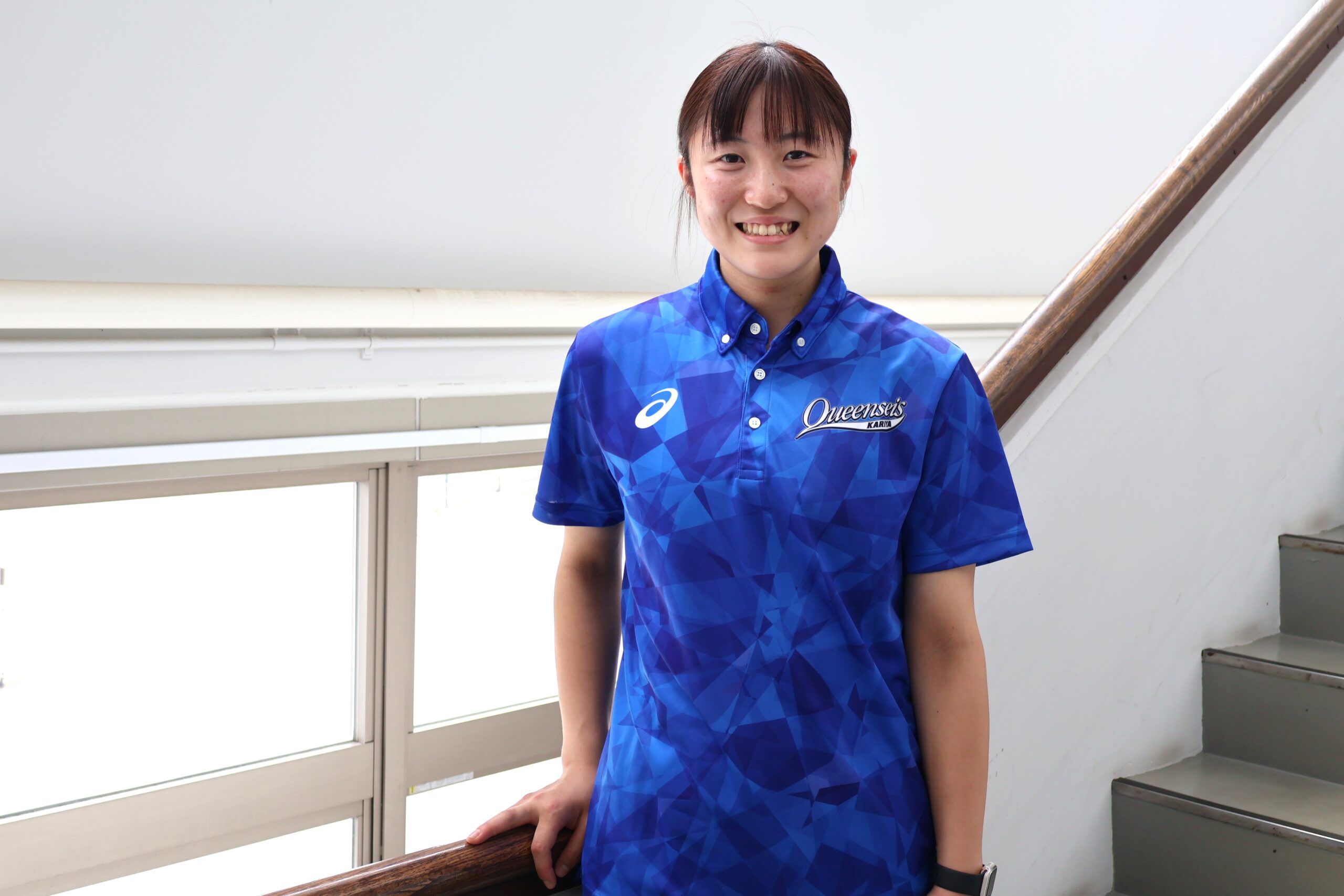
取材・文:田中 夕子