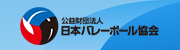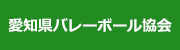人生初の試合で大号泣
149センチの守護神。コートに立つ彼女に“小さい”を加える必要はない。
どんなボールも上げてやる。負けん気がメラメラと伝わるような背中と、抜群の運動神経。ルーキーイヤーから、中村悠はクインシーズのコートでリベロとして抜群の存在感を放ち続けている。
表情を変えることなく、1球に集中する。自身のプレーで直接得点が取れるポジションではないからこそ、絶対得点を与えるものか、と守る背中は大きく、自信に満ち溢れているように見えるが、「全然そんなことはない」と謙遜ではなく苦笑いと共に否定するのは中村自身だ。
「できることよりもできないことばっかり。そもそも私、自信がないし、今までもずっとそう。負けず嫌いですけど、何で私がここにいるんだろう、って思うことばっかりでした」
バレーボールとの出会いは、小学2年の時。実は3年生からでなければ入部できない決まりだったが、「やりたい!」と押し切る形で特例として受け入れられた。
「最初は3年生からだったんですけど、私が入れてもらった後は、別に学年は関係ないね、という流れになって。2年生だけじゃなく1年生から入れるようになったので、ある意味先駆者です(笑)」
子どもの頃から運動能力は抜群に高かった。母に聞けば「1歳から駆け回っていた」そうで、スーパーへ買い物に行っても、ついた途端にあっという間に1人でどこかへ行ってしまう。「買い物に来ているのか、あんたを探しに来ているのかわからなかった」と未だに母から言われるほど活発で、動くのは大好き。バレーボールを始めてもすぐに運動能力を発揮して、さまざまなプレーを習得したが、出身地である京都市山科地区はバレーボールの人気も高く、後にSVリーグへ多くの選手も輩出されている。実は中村も、バレーボールを始めて間もない頃、最初に出場した公式戦である選手の洗礼を受けた。

「相手チームに林琴奈(現・大阪MV)さんがいたんです。年齢も上だし、当時からめちゃくちゃバレーボールがうまかった。今思えば、あんなスター選手なんだから手も足も出なくて当たり前なんですけど、2点とか3点しか取れない大惨敗。こてんぱんにやられたのが悔しくて、負けず嫌いなので大号泣したのを今でもよく覚えています(笑)」
中学に入っても当然バレー部で、練習に明け暮れる日々。3年になる頃、「もっとうまくなりたい」と求め、福井へ転校した。高校も福井県内へ進学しようかと考えたが、京都から福井へ渡ったように、「高校も新しい場所で挑戦したい」と考え、三重高校を選んだ。レシーブ練習を中心に、休日は朝から昼までトレーニングをして、昼食を終えたら13時半から20時までボール練習。平日も授業を終えて16時頃から20時半、21時を回るまで練習を重ねる日々を過ごし、1年時から春高バレーにも出場。翌年も全国の舞台を経験したが新型コロナウイルスが蔓延した3年時、インターハイや国体もない中、唯一の全国大会だった春高出場を逃し、高校生活を終えた。
高いレベルを求め筑波大へ「来るところを間違えた(笑)」
幼い頃から「将来はバレーボール選手になりたい」と考えていたが、漠然と描くだけで、このチームに行きたいとか、こんな選手になりたいと具体的に考えたことはない。高校を卒業してからの進路をどうするか。親元を離れて寮生活をしていたこともあり、最初は自宅に近い関西の大学へ通おうかと思っていたが、高校最後の年が不完全燃焼で終わったことも重なり「せっかくやるなら高いレベルで」と全国から選手が集まる関東の大学へ進学したいと考えるようになった。
とはいえ、じゃあどこに行くか、と言われてもわからない。
「そもそも情報が全然なくて、練習試合で行ったことのある大学や、日大とか日体大とか、名前を聞いてもすぐわかるところぐらいしかわからなかった。高校の監督に『筑波はどうだ?』と言われた時も、どこにあるのか、どんな大学なのかもわからなかった。勧められて初めて調べました」

どんな練習をしているのか。まずは体験を、と練習に参加した。1学年上には、よく練習試合をしてきた千葉の敬愛学園高OGの佐藤淑乃(現・NEC川崎)がいた。練習参加時だけでなくその後も大学の情報や、不安に思うことの相談など親身になってくれたこともあり、「筑波でやってみよう」と決意した。だが、入学早々にその決心が打ち砕かれそうになった、と笑う。
「レベルが高すぎて、正直、来るところを間違えた、と思いました(笑)。高校と大学はレベルが違うと頭ではわかっていたつもりでしたけど、パワーも球の強さも全然違う。(レシーブするために)コースへ入っていても吹っ飛ばされる。完全に、力負けしていました」
高校でトレーニングをしてきたとはいえ、専門的な知識があるわけではない。高校から大学、たった1学年の違いでも身体つきは大きく変わり、高さもパワーも違う。それでも「どうにかなる」と考えられるような楽観的な性格であればよかったが、うまくいかないことを気にするネガティブ気質であることは誰より自分が知っている。
「どれだけ悩んだか、というぐらい落ち込みました。親もすごく心配して『そんなにネガティブにならんと』と励ましてくれるんですけど、練習も試合もうまくいかない。1年生の頃はもちろん、2年の前半ぐらいまではずっと、『何で私はここにいるんだろう』と思いながらプレーしていました」
自信を得るためには結果を残すしかない。高いレベルの中で悩みながらも必死にもがいてきたが、優勝候補の一角として第2シードに入り、迎えた2年時の全日本インカレでは3回戦で福岡大に敗れた。練習試合では負けることがなかった相手に、大一番で負けたことも中村にとっては自信を得るどころか失うばかり。
「頭が真っ白で。大げさじゃなく、絶望しました」

全日本インカレの翌週には天皇杯があるとはいえ、4年生にとってはこれが最後のインカレ。悔しさに涙しながらも、上級生たちは労ってくれた。だが、労われれば労われるほど、思い通りのプレーができなかった自分や、負けてしまった事実ばかりに目が向いて、気持ちを切り替えることができない。自分を責めるばかりだったが、翌年になれば自分も上級生だ。チームを引っ張る最上級生がどう振る舞うべきか。最もわかりやすい形で示してくれたのが、1学年上の佐藤と主将を務めた大山遼(現・大阪MV)の存在だったと振り返る。
「4年生全員がすごく仲が良くて、その中心にいたのが遼さんと淑乃さん。大きな二枚看板がいたので、負ける気がしなかった。自分のことばかりじゃなく、周りのために動ける先輩たちだったので、私もこの4年生のために勝ちたい、と心から思っていたし、絶対に行ける、と信じていました」
有言実行とばかりにこの年の全日本インカレを制覇。1年前の悔し涙とは違う、歓喜の涙を流したが、喜びもほんの一瞬。何より頼もしかった4年生たちが抜ければ自分たちが最上級生になる。しかも人数は圧倒的に少ないうえに、中村は主将に就任した。
それまでもリベロとして、守備の要となりチームの勝利に貢献するために全力を尽くしてきた。だが大学最後の年、主将としての1年はチームをまとめ、引っ張ることも自分の仕事だ。
「自分が点を取って引っ張れたらいいんですけど、リベロにはそれができない。どうやってチームを底上げすればいいのか。自分のプレーの良し悪しだけじゃなく、チームを盛り上げるために何が大事なのか。すごく悩んだ1年でした」
未知数のSVリーグ「試合を通して成長できるように」

事あるごとに中西康己監督と話し、自分の中で答えを探すべく考える。何が正解かはわからない。でも、最も大事なのはチームの柱となる自分と、エースの門田湖都(現・群馬)、2人がいかなる時にも崩れずいることしかできないのではないか。そのためには、1つ1つのプレーの出来に落ち込むのではなく、もっと広い視野でチームを見ること。そして、点を獲るエースをレシーブと声で鼓舞し続けること。準決勝で東海大に2セットを連取されても「絶対に自分が決めて勝つ」とチームを引っ張る門田の姿に、上級生として何をすべきか。探してきた答えが見えた、と振り返る。
「中西先生からは『2人の存在がこのチームがどうなるかを決める』と言われ続けてきました。自分はネガティブで、うまくいかないと、どうしよう、と落ち込むだけだったんですけど、チームのために、と考えたら自分のパフォーマンスよりも大事なことがある。一番大事な試合で、何が何でも勝つ、とプレーする門田の姿を見て、こういうことだったんだ、って初めてわかった気がしました」
逆転で準決勝を勝利し、決勝は青山学院とフルセットの激闘を制し連覇を達成。得点を獲るエースを盛り立てた守護神は、最高の形で学生バレーを締めくくり、クインシーズ刈谷で新たなキャリアの一歩を踏み出した。

子どもの頃から憧れていた世界。バレーボールの楽しさを知る一方で、ステージが上がればまた課題にも直面する。
「パワーはもちろんですけど、サーブが段違いにすごい。大学に入った頃と同じように、今も(レシーブで)吹っ飛ばされています(笑)」
チームのために、と徹した大学最後の大会からまだたった1年。またルーキーとして歩み出すと、やはり自分のプレーがうまくいかないと落ち込むし、負ければ悔しい。でも、厳しい世界だからこそもっとこうなりたい、と描く自分の未来も浮かぶ。
「小さいからこそ存在感を大きく。今はまだ自分のことでいっぱいいっぱいですけど、物怖じしないリベロになりたい。44試合戦うことも未知数ですけど、でもとにかく思いきりプレーして、試合を通して成長できるように。終わる時には、新しいものをつかむことができた、と実感できるように、楽しみながら戦いきりたいです」
点を獲ることはできなくても、獲らせることはできる。誰より大きな闘志を秘めて。落ちる、と思うボールが上がる先には、きっと、中村の姿があるはずだ。

取材・文:田中 夕子